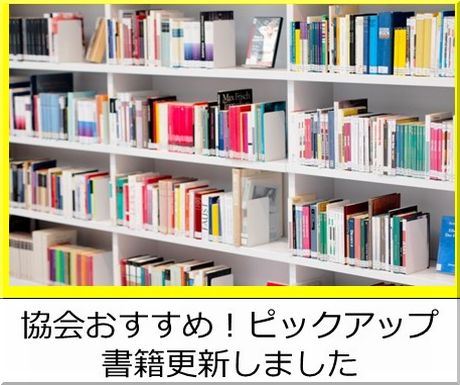深堀り!栄養士実力認定試験過去問題~食品衛生学~

食の安全に欠かせない「食品衛生学」。
過去問題の傾向から、
絶対に押さえておきたいポイントを挙げます👇
●食品と食中毒原因物質
細菌:腸炎ビブリオ、カンピロバクター、
サルモネラ、ボツリヌス など
ウイルス:ノロウイルス など
自然毒:テトロドトキシン---ふぐ🐡、
ソラニン---じゃがいも🥔の芽、
アミグダリン---青うめ、
ビタミンA---いしなぎ🐟の肝臓
フェオホルバイド---あわび
化学性:ダイオキシン類、抗生物質、
カドミウム、無機水銀、鉛
●食品と関連する寄生虫・原虫
アニサキス、トキソプラズマ、クドア
クリプトスポリジウム、肝吸虫 など
●食品と関連する寄生虫・原虫
●アレルギー表示が義務付けられている食品
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、
乳、落花生(ピーナッツ)
今回は、食中毒の予防についての問題を
見ていきましょう。
2023年問題36、正答率59.9%です。
Q
(2023年)問題36.食中毒の予防についての記述である。
正しいのはどれか。
(1) アニサキスは、冷凍(-20℃、24時間以上)
に対して抵抗性を示す。
(2) 黄色ブドウ球菌による食中毒は、食品の
加熱調理(80℃、20分間)により予防できる。
(3) ノロウイルスは、60℃、30分間の加熱
では不活化されない。
(4) フグ毒のテトロドトキシンは、加熱調理
(80℃、20分間)することで無毒化される。
⇒×(1)アニサキスは、-20℃、24時間以上の
冷凍で死滅する。
×(2) 黄色ブドウ球菌による食中毒は、
菌が増殖する際に産生されるエンテロトキシンが
原因である。この毒素は、熱に安定であり、
100℃、30分間の加熱でも無毒化されない。
◎(3) 【正答】
×(4) フグ毒のテトロドトキシンは、
熱に安定であり、100℃、4時間の加熱でも
無毒化されない。
(1)が寄生虫、(2)が細菌、(3)がウイルス、
(4)が自然毒ですね。
それぞれ、過去問に出てきたものを
ピックアップしていきましょう。
寄生虫と食中毒
食中毒の原因となる寄生虫は、
十分な加熱によって死滅します。
つまり、食中毒発生の原因は、
生食と加熱不足です。
また、-20℃以下の冷凍によって死滅する種類が
多いので、お刺身で食べる場合でも、
-20℃以下で24時間以上冷凍しておけば
かなり安心ですね。
ただ、家庭の冷凍庫は-18℃くらいです💦
過去問題に出てきた回数順に、寄生虫と
その原因食品を挙げていきます↓
☆アニサキスの幼虫
:スケトウダラ、マアジ、
スルメイカなどの海洋性の魚介類
☆トキソプラズマ: 豚肉
☆クリプトスポリジウム:飲用水
☆クドア:ヒラメ
☆肝吸虫:淡水産のカニ
(モズクガニ、サワガニなど)
☆横川吸虫:淡水魚(アユ、ウグイなど)
☆有鉤条虫:豚肉
☆日本海裂頭条虫:サクラマスなど
細菌と食中毒
食中毒の原因となる細菌は色々。
加熱殺菌できるものもあれば、
芽胞というシェルターで遺伝情報を守り、
熱に耐えるものもあります。
どうやって食中毒が引き起こされるのか
によって、3つに分類されます。
それぞれ、過去問題に出てきた回数順に、
細菌とその主な原因食品を挙げていきます。
<感染型食中毒>
細菌そのものが体内に入ることで、
食中毒を引き起こすもの。
☆カンピロバクター:鶏肉
☆サルモネラ:鶏卵
☆腸管出血性大腸菌O157:牛肉
☆エルシニア:豚肉
<毒素型食中毒>
細菌が食品中で出した毒素が体内に入ることで、
食中毒を引き起こすもの。
☆ボツリヌス:
嫌気性、芽胞を形成する
毒素(ボツリヌス毒素)は熱に弱い
いずし、芥子レンコン、瓶詰など
☆セレウス菌(嘔吐型):
嫌気性かつ好気性、芽胞を形成する
毒素(セレウスリド)は熱に強い
チャーハン、焼きそばなどの穀物類
☆黄色ブドウ球菌:
好気性
毒素(エンテロトキシン)は熱に強い
おにぎり、総菜など
<生体内毒素型食中毒>
体内に入った細菌が毒素を出すことによって、
食中毒を引き起こすもの。
☆腸炎ビブリオ:
嫌気性かつ好気性、低温では増殖できない
毒素(耐熱性溶血毒)は、加熱しても
一時的な失活しかしない
食中毒の発生は、夏期に集中している
海産魚介類など
☆ウエルシュ菌:
嫌気性、芽胞を形成する
毒素(エンテロトキシン)は熱に弱い
カレー、シチューなど
☆セレウス菌(下痢型)
嫌気性かつ好気性、芽胞を形成する
毒素(エンテロトキシン)は熱に弱い
プリン、ハンバーグなど
※「エンテロトキシン」は
熱に強いものも弱いものもある。
ウイルスと食中毒
食中毒の原因となるウイルスはいくつか
ありますが、何といっても最重要なのは
ノロウイルス!
過去問題に出てきたものを中心に、
ノロウイルスの特性、予防などを
確認していきましょう。
☆ヒトの腸管上皮細胞内で増殖
☆乾燥に強い
☆ウイルスが、10~100個でも感染する
☆経口感染&飛沫感染&接触感染
☆潜伏期間:48~72時間
☆症状:嘔吐、下痢、腹痛、吐き気、発熱
☆不活化には、中心温度85~90℃、90秒以上の
加熱が必要
☆冬季がノロウイルス感染症発生のピーク
☆ワクチンはない
自然毒と食中毒
フグ、毒キノコ、トリカブト‥‥
一般的にも知れ渡っている
致死性の高い毒を持った生物ですよね。
「ポイント」に挙げた5つは、
過去に複数回出題されているので、
症状などをチェックしましょう。
食中毒を起こす微生物の中で、肉眼で確認できる
身近なものは「アニサキス」です。
切り身で売っているタラにも、たまにいます。
ニョロニョロした白く短い糸くずのようなもの
が見えたら、それがアニサキス。
ちょっと気持ち悪いけど、ピンセットで取り除く、
あるいは、十分に加熱をすれば問題ありません。
お酢や塩やアルコールをかけても
死なないことを確認すると面白いかも…
因みに、我が家の息子は自由研究の実験で、
強アルカリ性の洗剤に漬けて死滅すること
を確認していました。
栄養士の就職先は色々ありますが、
食事の提供や、食品の開発に携わる方が
多いのではないでしょうか。
「食」にかかわる業務で、
食中毒、食品汚染、表示ミスは、
絶対に起こしてはいけません。
正しい知識と高い意識を持った栄養士として、
安心・安全な食を提供しましょう!
出典:栄養科学シリーズNEXT 食品衛生学 講談社
ゼロからわかる 栄養系微生物学 南江堂
全国栄養士養成施設協会が毎年実施する実力認定試験を
2024年12月実施分まで、過去5年間の問題を分野別に網羅。
直近2年は、実際の問題用紙を掲載。解説付き別冊解答充実。
5年間のすべての問題の正答率も示す。ご購入は建帛社様サイトから。
栄養士実力認定試験に関するお問い合わせはこちらからご入力してください。
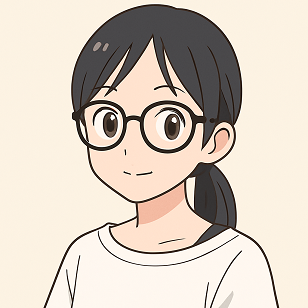
▶Columnist Profall
協会事務局スタッフ M・Y
管理栄養士
日本女子大学卒業
大手食品メーカーの研究職を経て、現在に至る。
3児のママ。