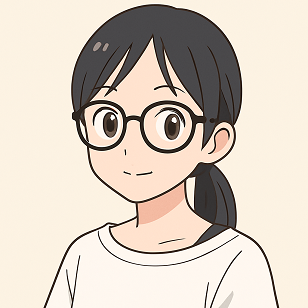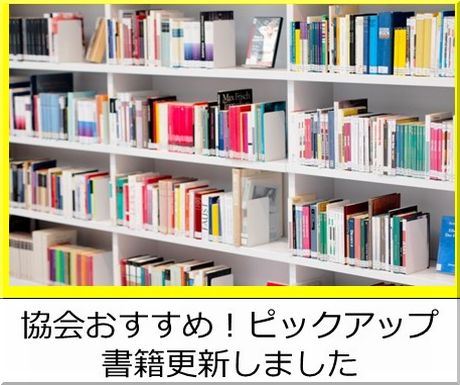深堀り!栄養士実力認定試験過去問題~生化学②~

生化学からの2回目の深掘りは、2024年の問題14、
アミノ酸とたんぱく質についての問題です。
正答率は63.6%。
Q
(2024年)問題14. アミノ酸とたんぱく質に ついての記述である。
正しいのはどれか。
(1) たんぱく質を構成するアミノ酸は、
D型である。
(2) 不可欠(必須)アミノ酸は、20種類である。
(3) α-ヘリックス構造は、たんぱく質の2次構造
の一種である。
(4) グルタミン酸は、塩基性アミノ酸である。
⇒×(1) たんぱく質を構成するアミノ酸は、
L型である。
×(2) 不可欠(必須)アミノ酸は、9種類である。
◎(3)【正答】
×(4) グルタミン酸は、酸性アミノ酸である。
アミノ酸・たんぱく質について、絶対おさえて
おかなきゃいけないポイント👇!
☆アミノ酸20種類の名前!
最低でも、不可欠(必須)アミノ酸9種は
覚えましょう!
☆たんぱく質の構造!
☆アミノ酸の代謝にかかわるキーワード!
アミノ酸がたくさんつながって
1つの分子となっているのが、たんぱく質です。
まずは、アミノ酸から見ていきましょう。
アミノ酸とは?
たんぱく質を構成するアミノ酸20種類は↓。
グリシン、アラニン、バリン、ロイシン、
イソロイシン、セリン、スレオニン、
アスパラギン酸、グルタミン酸、アスパラギン、
グルタミン、アルギニン、リジン、ヒスチジン、
システイン、メチオニン、フェニルアラニン、
チロシン、トリプトファン、プロリン
※体内で合成できない不可欠(必須)アミノ酸は
ピンク色
アミノ酸の基本構造は、【炭素(C)にカルボキシ基
(-COOH)とアミノ基(-N H₂)、水素(H)が結合
した主鎖】+【そのアミノ酸の性質を決める官能基
(側鎖)】。
炭素(C)は他の物質とつなげる手を4本持って
います。
この4本の手のうち、一本がつないでいる「側鎖」
の種類や構造、手をつなぐ位置で分類されます。
分類について、過去問題にあるものを挙げてみます。
それぞれ、覚えておきたい物質名をチェックしましょう!
側鎖の位置:L-型とD-型に分類される。
たんぱく質を構成するアミノ酸は20種類で、
すべてL-型。
側鎖の性質:
・分岐鎖(分枝)アミノ酸
→バリン、ロイシン、イソロイシン
・芳香族アミノ酸→トリプトファンなど
・含硫アミノ酸→メチオニンなど
・酸性アミノ酸→グルタミン酸、アスパラギン酸
など
・塩基性アミノ酸→リシンなど
・脂肪族アミノ酸→グリシン、アラニンなど
さらに、代謝されていったときに、
糖質と脂質のどちらの代謝経路に
組み込まれるのかによっても分類されます。
過去問題にあるのは↓です。
・ケト原性アミノ酸(脂質の代謝経路へ)
→ロイシン、リシン、イソロイシンなど
・糖原性アミノ酸(糖質の代謝経路へ)
→糖新生に使用されるアミノ酸
アミノ酸が2~49個くっついているのが
「ペプチド」!
50個未満のアミノ酸がつながっているものは
「ペプチド」と言います。
アミノ酸2個でジペプチド、3個でトリペプチド、
10個以上でポリペプチド。
栄養士さんに馴染み深いホルモン、
インスリンやグルカゴンは「ペプチド」です。
アミノ酸が50個以上くっついているのが
「たんぱく質」!
つまり、長くつながった高分子のペプチドのことを
「たんぱく質」と言います。
つながって(一次構造)、
立体的に折れたりねじれたりして(二次構造)、
複雑に折りたたまれて(三次構造)、
それがさらにくっついて(四次構造)、
と様々な形のたんぱく質になります。
たんぱく質、アミノ酸の代謝について
問題は分類と構造についてですが、
代謝についても生化学で重要な項目です。
糖質よりややこしいかも…
と思っている方もいるかもしれませんが、
簡単なポイントだけあげておきます。
・たんぱく質はトリペプチドからアミノ酸といった、
小さい分子に分解されてから代謝される。
・たんぱく質の分解(消化)は胃と小腸で行われ、
小腸で吸収される。
・アミノ酸は、エネルギー源=ATPを生産する
・アミノ酸は、体たんぱく質の原料なので、
常に蓄えが必要。血中には一定量のアミノ酸がある。
この状態をアミノ酸プールという。
・アミノ酸の代謝・合成を制御する反応を
アミノ基転移反応という。
・アミノ酸の代謝によって生じたアンモニアは、
肝臓のオルニチン回路でATPを使いながら
無毒化され、尿素となり、尿中に排出される
アミノ酸・たんぱく質について、
整理できたでしょうか。
アミノ酸の名前は、栄養機能食品のCMや
パッケージなどでよく見かけるものもありますよね。
我が家のサッカー部男子たちも、コーチから
「試合前にBCAAゼリーを飲め!」と言われています。
「BCAAって何?」と聞かれたら、栄養士としては、
「バリン、ロイシン、イソロイシン!」と
即答したいところ。
さらに、「体内ではつくれない不可欠(必須)
アミノ酸で、さらに、筋肉でエネルギー源になれる
分岐鎖(分枝)アミノ酸だよ!」と答えられたら、
さすが栄養士!って思ってもらえます✨