深堀り!栄養士実力認定試験過去問題~食品学総論~

さて、「食品学」です。
栄養士を目指す皆さんが好きであろう
「食べ物」そのものです😊
食品学総論、過去問題の傾向から、
絶対に押さえておきたいポイントを挙げます。
●日本食品標準成分表の基本的な見方
●食品中の水(自由水、結合水、水分活性)
●食品中の五大栄養素は、
どんな性質か
どんな食品に多いか
●呈味成分
●色素成分
五大栄養素の性質は、生化学と重なる部分も
あります。
丸暗記ではなく、「これ何だっけ?」と思ったら、
ぜひ生化学のテキストも確認してみましょう!
今回の「深堀り」するのは、
「水分」の問題です。
2024年問題23、の正答率は63.2%でした。
Q
(2024年)問題23. 水分活性についての記述である。
正しいのはどれか。
(1) 水分活性は、結合水の割合が大きいほど
高くなる。
(2) 水分活性の最大値は、100である。
(3) カビは、細菌よりも低い水分活性で
繁殖できる。
(4) 食品中の脂質の酸化は、水分活性の影響を
受けない。
⇒×(1)水分活性は、自由水の割合が
大きいほど高くなる。
×(2) 水分活性の最大値は、1である。
◎(3) 【正答】
×(4) 食品中の脂質の酸化は、水分活性の
影響を受けない。
「水分が多いから、口当たりが良くて食べやすい」
「水分が少ないから、日持ちする」
などなど、水分は、食事や買い物での食品の選択
にも影響する、身近で分かりやすい成分です。
食品の水分が「多い」「少ない」って、
どんなことなんでしょうか。
食品の水分についてのポイント👇です。
☆他の成分(糖質やたんぱく質)と
くっついていない、
フリーな状態の水が「自由水」
☆他の成分とくっついた状態の水が「結合水」
☆「自由水」と「結合水」の割合を示すものさし
が「水分活性」
☆「水分活性」が低い食品は保存性が高い
それぞれ見ていきましょう。
他の成分とくっついてない「自由水」
フリーな状態の「自由水」は、
まさに「水」らしく、
低温(0℃以下)になれば氷になり、
高温(100℃)になれば水蒸気になります。
そして、食品中の微生物が元気に過ごし、
増えていくために利用できるのも、
「自由水」です。
他の成分とくっついている「結合水」
「結合水」はフリーではないので、
低温(0℃以下)になっても凍らず、
高温(100℃)になっても蒸発しにくい。
そして、微生物が利用できません。
「自由水」と「結合水」の割合を示すものさし・
「水分活性」
「水分活性」をちゃんと理解しようとすると、
蒸気圧の話になります。
「気圧…」と高い壁を感じる人もいるかも…💦
なので、ざっくり
『「自由水」と「結合水」の割合を示すものさし』
と覚えましょう。
<水分活性のポイント👇>
・水分活性の値は、「0~1」
・純水の水分活性は「1」
・自由水の割合が多い⇒水分活性は「大」
・結合水の割合が多い⇒水分活性は「小」
「水分活性」が低い食品は保存性が高い
水分活性は、微生物の増殖、酵素活性、
脂質の酸化に影響を与えます。
<微生物>
・水分活性が低いと、
一般的に微生物は 増殖できない
細菌→0.8弱くらいで×
酵母→0.75くらいで×
カビ→0.7弱くらいで×
<酵素>
・水分活性が低くなると、酵素活性も低くなる
<脂質の酸化>
・脂質の酸化は、水分活性0.3までは
低下に伴って起こりにくくなる。
・脂質の酸化は、水分活性0.3以下になると、
低下に伴って起こりやすくなる。
水分活性が適度に低く、保存に適当な状態なのに、
乾物のように水戻しをしなくても食べられる
食品を「中間水分食品」といいます。
中間水分食品は、水分活性0.65~0.85。
塩漬けや砂糖漬け、ジャム、魚の干物など、
「美味しく長持ち」の工夫として
つくられてきた食品には、
中間水分食品がたくさんあります。
昔の人は、経験の中で食品の水分を調整し、
保存食を生み出してきたんですね✨
出典:サクセス管理栄養士講座 食べ物と健康Ⅰ
第一出版
全国栄養士養成施設協会が毎年実施する実力認定試験を
2024年12月実施分まで、過去5年間の問題を分野別に網羅。
直近2年は、実際の問題用紙を掲載。解説付き別冊解答充実。
5年間のすべての問題の正答率も示す。ご購入は建帛社様サイトから。
栄養士実力認定試験に関するお問い合わせはこちらからご入力してください。
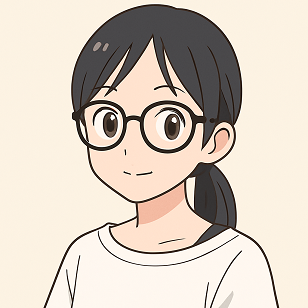
▶Columnist Profall
協会事務局スタッフ M・Y
管理栄養士
日本女子大学卒業
大手食品メーカーの研究職を経て、現在に至る。
3児のママ。




![くらしき作陽大学 食文化学部 [臨床栄養分野] 教授、准教授または講師を募集しています](https://www.eiyo.or.jp/dcms_media/image/news_251022.jpg)
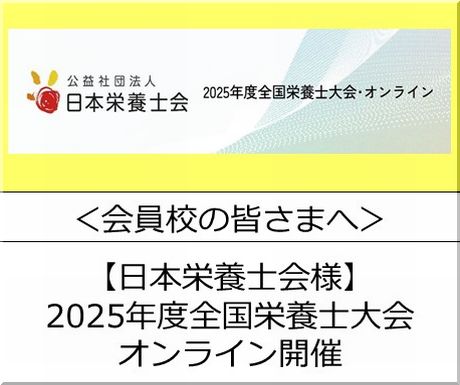
![松本大学 人間健康学部 健康栄養学科[基礎科学分野] 教授、准教授、専任講師を募集しています](https://www.eiyo.or.jp/dcms_media/image/news_251020_2.jpg)