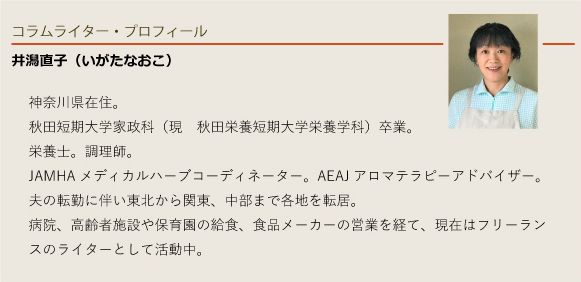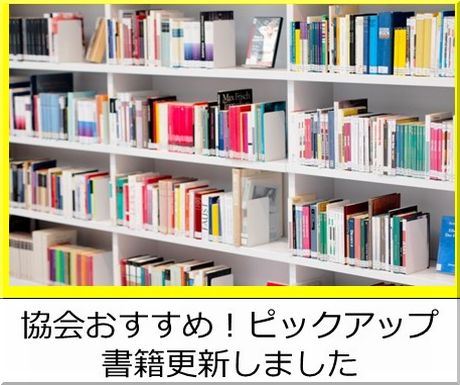<おいしい情報をお届けするコラム>甘いだけじゃない!砂糖の優れた力を上手に利用しよう

砂糖の発祥は紀元前のインドです。日本に伝わったのは奈良時代。明治時代以降、高級調味料として一般家庭に普及し始めました。
さとうきび(かんしょ)とさとうだいこん(ビーツ・てんさい)が原料。日本では、主にさとうきびは沖縄県と鹿児島県で、さとうだいこんは北海道で栽培されています。
砂糖の原料はさとうきびやさとうだいこんを加工した原料糖で、不純物を取り除いて精製したものが砂糖です。日本では原料糖の3分の2を輸入しています。

上白糖や三温糖などの「車糖(くるまとう)」、グラニュー糖や中ざら糖などの「ざらめ糖」、氷砂糖や粉砂糖などの「加工糖」などがあります。
三温糖は上白糖より体にいいって本当?
上白糖と三温糖の製造方法は同じです。製造過程で上白糖が先にできます。残った原料糖をさらに煮詰めて三温糖が作られます。茶褐色になるのは加熱工程を繰り返すことでカラメル化するため。加熱処理の回数が多いことを三回温めることに例えて三温糖と名付けられました。上白糖と三温糖の栄養成分はほとんど変わりません。
上白糖は純度が高く癖がないので、料理やお菓子作り、飲み物など何にでも合います。使い分けるとしたら、微量のミネラルを含む三温糖は独特な風味とこくがある甘さを生かして和食料理に。
なぜ疲れを感じた時は甘いものが食べたくなるの?

砂糖の主成分であるショ糖は、ブドウ糖と果糖が結合してできた二糖類。穀物や麺類のような多糖類に比べて、体内で単糖に分解されるのが早いため吸収が早くなります。
脳や筋肉の栄養源はブドウ糖。疲れを感じた時に「甘いものが食べたい」と思うのは体の自然な欲求です。
脳にはブドウ糖を貯蔵することができないので、勉強や運転などで疲労した時に甘いもので栄養補給すると即効性があります。ブドウ糖は筋肉と肝臓にグリコーゲンとして備蓄されていますが、スポーツや肉体労働などで急激に消費されると持久力が低下して肉体疲労が起こります。甘いものを食べると体内で素早くエネルギーに変換されて、体力の持続と疲労回復に効果的です。
砂糖は虫歯や肥満、糖尿病の原因?

砂糖は虫歯や肥満、糖尿病の直接の原因ではありません。
虫歯予防のためには食後や就寝前に口内を清潔にすることが大切です。肥満防止のためには、適正体重を知り、習慣的な運動とバランスの良い食生活でコントロールしましょう。
糖尿病の発症には遺伝的要因や生活習慣と食事のバランスの乱れが関連しています。
肉をやわらかく!卵焼きをふんわり!
砂糖のには調味料としての多様な機能があります。
すき焼きの肉が硬くなるのを防いだり、卵焼きをふんわりさせたりするのは、砂糖がたんぱく質と水を結びつける親水作用です。すし飯や餅菓子などが時間の経過とともに硬くなるのを防ぐのはでんぷんの老化防止作用です。ジャムやようかんが長持ちするのは防腐作用で、かびや細菌が繁殖するために必要な水分を砂糖が吸収してしまうからです。
砂糖は長期保存しても変質しないので、JAS法で賞味期限を表示する必要がないとされています。
今回の、おいしいレシピは「牛肉の佃煮」!

牛肉にあらかじめ砂糖をまぶしてやわらかく仕上げます。
<牛肉の佃煮>
1回に作りやすい分量です(約5人分を目安にしています)
牛肉は脂身が少し入った切り落としなどの薄切り肉を使用します
【材料】
牛肉の薄切り 300g
しょうが 40g
砂糖 大さじ2と1/2
醤油 大さじ4
みりん 大さじ1
酒 大さじ3
☆材料の計量のポイント:しょうがのひとかけは親指の頭程度の大きさのことで約15g。今回は3かけ程度を使用します
【作り方】
(1)しょうがは皮をむいてせん切りにして、さっと水にさらして、ペーパータオル等で水気を切っておきます
(2)牛肉に砂糖をまぶしておきます
(3)醤油とみりんと酒を合わせておきます
(4)冷めたフライパンに(1)の牛肉を入れてから中火にかけます。牛肉の脂身で炒めることで焦げ付きませ
ん。ほぐしながら炒めて、牛肉の色が変わったら(1)のしょうがと(3)の調味料を入れて、時々混ぜ
ながら約10分間煮て汁気を飛ばします
冷蔵庫で1週間程度保存できます
冷蔵保存すると牛脂が白く固まりますので、食べる前に電子レンジで少し加熱しましょう
(1人分 359kcal 塩分2.1g)