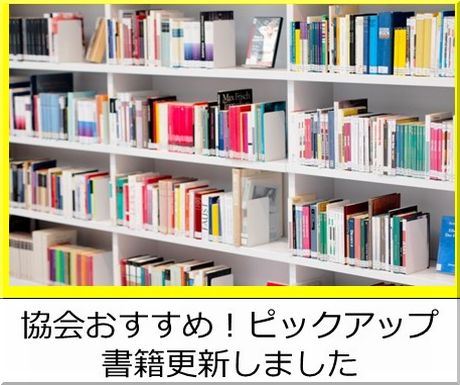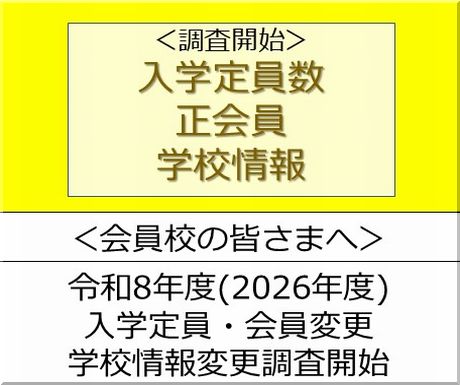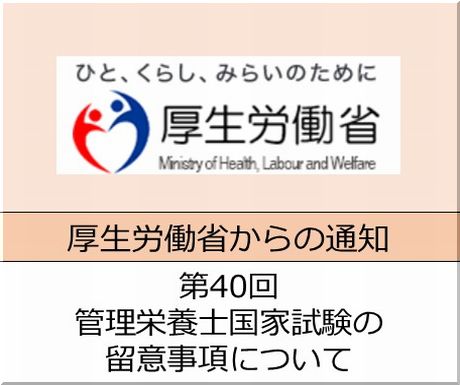深堀り!栄養士実力認定試験過去問題~栄養学各論~

胎児から高齢者まで、身体の変化に伴い、
適切な食生活は変わっていきます。
それぞれのライフステージで、
どのような身体的特徴があり、
どのような食生活をしていくべきなのか
を学ぶ、栄養学各論です。
過去問題の傾向からわかる、
絶対に押さえておきたいポイントです👇
●「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
策定の背景、BMI、年齢区分、参照体位、
耐容上限量(UL)、推定平均必要量(EAR)、
推奨量(RDA)目安量(AI)、 目標量(DG)
●「妊娠前からはじめる
妊産婦のための食生活指針」
妊娠前、初期、中期、後期の特徴
食生活の注意点
●「授乳・離乳の支援ガイド」
母乳栄養、離乳食、乳児の成長・発達
●高齢期について
身体的・生理的特徴、フレイル予防
今年度は、「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
が策定されました。
食事摂取基準を活用するための基本的な知識を
再確認しておきたいですね。
と、いうことで、今回は「日本人の食事摂取基準」
についての問題を見ていきます。
2020年版に基づく問題ですが、
2025年版にも共通しています。
2024年問題46、正答率は70.0%。
Q
(2024年)問題46. 「日本人の食事摂取基準
(2020年版)」についての
記述である。正しいのはどれか。
(1)エネルギー収支バランスの指標に、
成人ではBMIを用いる。
(2)目安量(AI)は、生活習慣病の発症予防を
目的とした指標である。
(3) 高齢者の年齢区分は、65歳以上の1区分
である。
(4) 参照体位は、目標とする体位を示している。
⇒◎(1)【正答】
トリグリセリドの合成が促進する。
×(2) 目安量(AI)は、栄養素の摂取不足の
回避を目的とした指標である。
生活習慣病の発症予防を目的とした
指標は、目標量(DG)である。
×(3) 高齢者の年齢区分は、65-74歳と
75歳以上の2区分である。
×(4) 参照体位は、性及び年齢区分ごとに
設定された日本人の平均的な体位
(身長・体重)を示している。
「日本人の食事摂取基準」とは?
厚生労働省から出されている
エネルギーと栄養素の摂取量に関する
ガイドライン。
健康の保持・増進、
生活習慣病の発症・重症化予防のために
参照にするべき基準です。
どんな栄養素を、どれくらいの摂取するように
示されているのか…といった詳細を
正しく読み取るためにも、基本の理解は必須!
ということで、過去問題に出てくる基本を
見ていきましょう。
★健康増進法に基づいている
★エネルギー収支バランスの指標⇒BMI
★摂取不足の回避のための基準
⇒①推定平均必要量(EAR):50%の人が◎
②推奨量(RDA):ほとんどの人が◎
③目安量(AI):科学的根拠が不十分だけど、
不足状態の人はいない
★過剰摂取による健康障害の回避のための基準
⇒耐容上限量(UL)
★生活習慣病の発症予防のための基準
⇒目標量(DG)
★参照体位⇒◎平均的な体位
✖最も健康的な体格
★高齢者の年齢区分
⇒①65-74歳
②75歳以上
2025年版から加わった「骨粗鬆症」
2020年版から2025年版で変わった点の一つは、
食「生活習慣病等」に「骨粗鬆症」が加わったこと。
骨粗鬆症は、エネルギー・栄養素との関連が深く、
また、発症・重症化することで
「生活機能の維持・向上」の大きな障害となります。
特にハイリスクなのは、更年期以降の女性。
女性ホルモンの1つエストロゲンの分泌低下が
骨量の低下につながる。
骨量のピークは20歳頃だから、
若い時に骨量を増やしておくことが大切。
骨量の維持にかかわる栄養素はカルシウム、
ビタミンD、ビタミンK、などです。
でも、どれも「目標量」を設定するには、
根拠が不十分。
カルシウムは、推定平均必要量と推奨量が
設定されています。
ビタミンDとビタミンKは、
推定平均必要量と推奨量を設定することも
難しく、目安量が設定されています。
解剖生理学で学ぶ骨形成・骨吸収、
栄養学総論で学ぶカルシウム、
ビタミンD、ビタミンK、
臨床栄養学で学ぶ骨粗鬆症の予防・治療。
それぞれの教科書と照らし合わせながら
「日本人の食事摂取基準(2025年版)」を
読んでいくと、「なるほどなぁ」と思えたり、
「根拠」の研究が気になったり…
興味深いですね✨
出典:健康・栄養科学シリーズ 応用栄養学 南江堂
栄養科学イラストレイテッド 応用栄養学 羊土社
日本人の食事摂取基準2025年版 第一出版
全国栄養士養成施設協会が毎年実施する実力認定試験を
2024年12月実施分まで、過去5年間の問題を分野別に網羅。
直近2年は、実際の問題用紙を掲載。解説付き別冊解答充実。
5年間のすべての問題の正答率も示す。ご購入は建帛社様サイトから。
栄養士実力認定試験に関するお問い合わせはこちらからご入力してください。
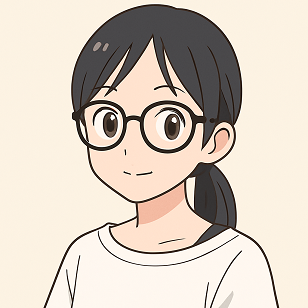
▶Columnist Profall
協会事務局スタッフ M・Y
管理栄養士
日本女子大学卒業
大手食品メーカーの研究職を経て、現在に至る。
3児のママ。